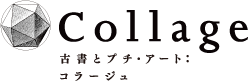「万物は変化するという言葉がある。しかし、天の下、変化するものなしともいう。いずれの常套句も一面の≪真理≫ではある。構造というものは、珊瑚礁にも似て、比較的長い期間にわたって確固として動かない人間関係のことであるが、同時にそれは、生まれ、成長し、やがて死に至る生きものでもあるからだ。
社会変動の研究という言葉は、社会諸科学の総合の意味にも用いられようが、そうでなければ、もっとも変化しにくい現象の変化の研究というくらいの意味に限定して使用すべきであろう。とはいえ、変化しにくいということの意味そのものも、歴史上の時と所によって変化しうるものであるわけだが。
世界を対象とする社会科学の主要な論点のひとつは、人類史にもいくつかの大分水嶺があったのだということである。たとえば、社会科学者は滅多に取り上げないが、広く認められているこのような分水嶺のひとつに、いわゆる新石器革命、つまり農業革命がある。さらに、いまひとつの分水嶺が、近代世界の誕生である。
後者こそは、現代のほとんどの社会科学がその理論構成の中核をなす対象として措定している出来ごとである。十九世紀の社会科学にとっても、事情は同じだったといえよう。実際、近代を規定する要因は何か≪ひいては、近代はいつ始まり、いつ終るのか≫、という問題をめぐって、えんえんと議論が続けられてきた。しかも、この変化を推進した原動力が何であったかについても、見解が分かれている。もっとも、過去数百年の間に、世界には大きな構造変化が生じたことや、そうした構造変化の結果、今日の世界はこれまでの世界とは異質なものになっていることくらいについてなら、広汎な意見の一致がえられよう。歴史の進歩を確信する進歩史観は拒否する人でも、歴史に構造変化があるくらいのことは認めるはずだからである。
この構造の≪変化≫を記述したり、その原因を説明するには、どのような単位の社会を研究対象とすればよいのか。ある意味では、現代の社会科学上の理論にかかわる論争の多くは、つまるところこの問題に帰着するともいえる。この問への解答こそは、現代の社会科学がもっとも希求してやまないものである。・・・」