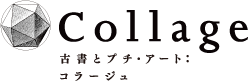鶴見和子さんとたまたま同じテーブルについたことがあった。『心の花』の何かの祝いの会であったのか。『心の花』とは近代短歌の先駆者のひとり、佐々木信綱先生の「竹柏会」という短歌結社の機関誌であり、明治31年創刊、最も伝統のある歌誌ともいえた。今は思想家、社会学者である鶴見さんが、かつて少女の日、その「竹柏会」に所属し、信綱門下として歌を学ばれたことがある、という程度の知識はわたしにもあった。
中略
その鶴見さんの同じく少女だった日に、『虹』という一冊の歌集がある。昭和14年8月、「竹柏会」刊行となっているから、集められている作品は10代の終りから20代の初めにかけてのものなのか。日本における学業を終え、アメリカ留学を前にしての歌集と自ら記すが、それに師である信綱先生も「英文学にいたくふかく、かつはみ国ぶりの舞踊にたくみに、わが藤波会の同人としては、なよよかなる言葉もてよく歌を品騭(ひんしつ)し、軽井沢の山荘に遊びては、馬を落葉松の林に馳騁す。動と静と、剛と柔と、二つの性を兼ね備ふ」などと、愛情に満ちた序文を寄せておられる。
そうして、歌集の作品の多く、その序文によりほぼいい尽くされているといえ、たとえば、
狂ほしさ天馬を駆らむ空よぎりそのいや果てに生命死すまで
成るを恋ひはた成るをおそれ我が夢は追い求めてぞあるべかりける
など、その日の日本の、最も高度の知的環境にあって育った一少女の典型的な抒情の範囲のものであるが、ただ巻末に近く、
幾万の髑髏の一つ崖土にちらと覗きて我を避けしむ
のように、一種の乱れ、ないしは動きを見せていくのが注目される。中国旅行詠の中のものであり、その日にそこにはすでに日本の侵略戦争の現実があった。乱れないし動きは、同時に彼女の心の中に目覚めていくものでもあったのだろう。
そうした『虹』の刊行直後、アメリカに留学する。1939年であるなら、もはや険しい政治状況下なのか。その間、鶴見さんの短歌がどうなっていったのか、わたしに知る資料はない。わずかに知り得るのは戦後の『昭和万葉集』というアンソロジーのうち、第5巻に採録されている次の一首だけである。
我が国に大きな変動の起らむを潜みて遠く我学ばむか
……詞書があり、それによると、1941年、コロンビア大学に学んでいて、日米関係の険悪化に伴い日本領事館により帰国を勧告されたときのものという。一首にある佶屈の調べは、やがて来る戦争危機、ないしは祖国である日本の運命を見ている不安を告げるのか、「潜みて」というのがやや判らなかったが、帰国者を乗せるため日本を出港したという竜田丸という船が、おとり船であって到着することなく、彼女自身学籍を抜いたままその国に残留を余儀なくされた事情が背後にあった。そうであれば、「遠く我学ばむか」としてそれにつづく言葉の意味も、ここでは重く、彼女の置かれた位置と共に、その日の切迫感をよく告げ出しているといえる。
そうしてその一首の後に、彼女の短歌がどうなっていったかを再び知らない。戦後の鶴見さんの生き方は知られている通りであり、多くのことが書かれてもいるが、ただ、短歌には短歌だけが伝え得る、人間内面の深奥のものがある。……
近藤芳美「歌集『虹』とそれ以後」(「思想の科学」鶴見和子研究、1996年2月)より