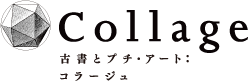本サイトは、言語的及び非言語的表象による知性と感性の融合を通じ、世界やそこに生きる人間存在について、思索する機会の創出を目的としているが、右記にて日本の作家(詩・小説)と美術家のコラボレーションによる詩画集の事例の一部を紹介します。
「ほかの国々の文明・文化についてはいざ知らず、日本では、詩歌・文章と美術との関係は非常に古い時代からきわめて密接だったと言っていいだろう。
『源氏物語』「絵合」の巻は、光源氏が後見をしている斎宮女御と、頭中将の娘で斎宮女御よりも先に冷泉帝に入内していた弘徽殿女御との間で争われる絵巻物の傑作くらべを、生彩ある筆致でみごとに描いている。・・・その間双方がさかんに自陣の絵巻の優秀さをたたえ、相手方の絵巻の欠点を言いたてる言葉争いもあって、紫式部という作家が、11世紀初頭における堂々たる美術批評家であったことを示しているといってよい。
全世界的な視野に立って見ても、物語の中でこれほど洗練された絵画鑑賞論が展開されているケースは稀だろうと思われる。・・・
こういう部分を読むと、日本の美術がいかに言語文化の洗練と歩調を合わせて発達してきたかを思わずにはいられない。紫式部より一世紀先に生きていた紀貫之の時代には、上級貴族らの邸宅はすでに屏風という形の詩画集の全盛期だった。貫之の歌集の中には、屏風に書かれた屏風歌―もとよりすべてが注文制作―が数多く収録されている。屏風歌とは、しかるべき貴族の50歳とか60歳とかの賀のため、あるいはその他さまざまな機会に新調された、当代一流の画家による屏風絵に付け合わせて詠まれた歌のことで、こららの歌は屏風上に囲いこまれた色紙形の中に書き加えられ、詩画一体の観賞用工芸品がそこに出現したのである。・・・
絵巻とい形式が日本で数百年にわたってきわめて顕著な発達をとげたということは、それが現代の日本人にとっても相変わらずきわめて親しい鑑賞的態度の典型を示していたことを意味する、とはいえないだろうか。
日本で、美術と言葉が結びついた美術作品の分野において、数々の息を呑むような傑作が作られたことは、こういう歴史的背景を考えれば当然だろうと私は思う。・・・
こうして見れば、近代・現代の美術家および詩歌文芸界の志ある人々が、苦闘に次ぐ苦闘を重ねなければ、この長い伝統の重圧をはねのけて自分たちの個性が強烈に輝き出ている詩画集・オブジェのたぐいを制作することはできなかった、という経緯もおのずと明らかだろう。・・・」
大岡信『日本の美術と言語芸術の関わりについて』(『本の宇宙』展カタログより)