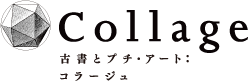1956年秋第一回アジア作家会議に出席するため著者がインドに滞在した際、感じ考えた≪思想≫旅行記。
「・・・日本と西欧、このユーラシア大陸の極東にある島と、極西にある半島。そのまんなかにある広大で大々的なるモノ。文化文明における古代史上代的な秩序というところでは、われわれの祖先は、この大々的なモノに学んで、それを取り入れた。ヒマラヤの向こうの山の方から、三蔵法師がひょっくりと出て来るような気がする。遣唐使たちが、そのまた向うの方でウロウロしているように思う。ところが、文化文明における近代史現代史的秩序においては、われわれ日本人は、この広大なる地域を、たとえば腰にぶらさがっていたオモシを、ドサッとばかりおっことしてしまうような工合で、もっぱら西欧にとりついた。今度は三蔵法師ではなくて、黒船であり、咸臨丸である。
アジアは、わえわれからおっこちてしまったのである。しかし、まるでおっこちてしまったわけではあるまい。まだ遅くなはいであろう。ベンチに坐っていて、私は、たとえば足のない人が、手術なんぞ切りおとしてなくなってしまったその足が疼くという、あの気持ちを味った。
ない足が疼く、あるいは痒くなる。その痛みや痒さをどうにかしようと思って手を出そうとすると、その足は、伝統として、歴史として、古代史、あるいは上代史的な精神秩序として、実在としてあるにはあるけれども、近代現代的な精神、文化の秩序としては、ないみたいな気がして来る、あるいは、あってもらっては困るような気がして来る。古代史上代史的秩序における同質性と、近代史現代史的秩序における異質性。
文化創造の上でのわれわれの苦しみは、まず、このようなことになるものなのではなかろうか。」