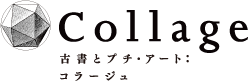哲学は、現実としての≪悪≫の問題にどのように迫り得るのか。
「・・・どうして悪は、あるべからざるものでありながら、そこにある種の魅力があるのだろうか。その点を避けるとき、≪悪≫の問題を扱ったことにならないだろう。およそ、暴力や破壊に対するひそかな快感や隠れた欲望は、われわれ人間にとって決して偶然的なものでなく、人間の本能的自然のうちに深く根ざしている。さらにいえば、根源的な自然がわれわれ人間に破壊をすすめ、≪悪≫を促すのである。
これまで、哲学や倫理学においては≪悪≫の問題がうまくとらえられず、宗教や芸術においては、突っ込んで扱われたのは、いったいなぜだろうか。おそらく、宗教や芸術の方が≪悪≫の持つ魅力あるいは魔力をうまく掬い上げているからであろう。いま、宗教や芸術と哲学や倫理学とを対立させたが、むろん、問題はそれらの領域そのものにあるのではない。むしろ、そこでの言説の形態の違いにあるのである。
その点で私が手がかりにしたいのは、ほかならぬサド、マルキ・ド・サドである。サドほど、人間の自然の怪異性を醒めたかたちで明るみに出した人はいない。サド侯爵は、永い間の牢獄その他の幽閉生活のなかで、想像力のかぎろを尽くして世のいわゆる良識や道徳に背き、悪事、淫行、残虐のうちに快楽を求める奇怪で異常な人々の振舞いを描きだした。そこでは、根源的な自然を離れた無難な美徳は、人間を弱々しく不幸な境遇に導き、反対に、悪徳こそ自然に基づいた活力と繁栄をもたらすとされた。
自然の秘密を暴いたサドの世界では、美しさよりも醜さが尚ばれるが、それは、美とは単純でつまらないものであり、それに反して、醜さは異常で人に心をときめさせるからである。美とかみずみずしさとかは、せいぜい単純な感覚に訴えるにすぎない。ところが、醜さや奇怪さは、はるかに強烈な刺激をわれわれの感覚に与える。その結果、われわれの感性の活動もいっそういきいきしたものになり、興奮も高まるのだ、と彼は書いている。・・・」