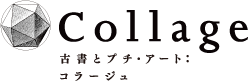フランスという名で呼ばれている文化の考古学(アルケオロジー)。
「・・・蓮實さんとぼくとで、ここまで主として十九世紀の話をしてきたんだけれど、それは現代のフランスが拠って立つ地平がまさに十九世紀につくられたのではないかと考えるからであり、・・・一方、その十九世紀という時代そのものが、とりわけ歴史に関心を持ち、自らの起源を求めていった時代だった。・・・歴史というものが単に書かれる歴史ではなく、人類を突き動かしてゆく大きな動きとしてとらえられてくる。いわば大文字の≪歴史」が、十九世紀のとくに後半を支配する。ヘーゲルが人類の精神の歴史を己が哲学で集約してしまうのと同様に、マルクスは社会の歴史的発展を集約してしまう。そして、そこから未来への投企が必然性の相をもって語られる。
しかし、逆説的なことに、そういう一種の普遍的な歴史がヨーロッパ人に共有されはじめたとき、同時に植民地とか万博博という形でヨーロッパの外の空間が拡大してゆき、それと知らずにヨーロッパの墓穴を、政治の上でも≪知≫の上でも掘ってゆく。はじめヨーロッパ人は、ヨーロッパの歴史を貫いていると考えられる時間に従って未知の空間を切りとり、それを発展段階の遅れた野蛮として見てゆく。ところがやがて、十九世紀末から二十世紀にかけて、非西洋を野蛮として見てはいられなくなってくる。ただ、はじめのうちは、そこに固有の時間と空間を認めるというよりは、それらの≪外部≫がより始原に近いからより真実を含んでいて、より刺激である、という発想だったように思う。・・・未開社会の未開性が、より本源的なものを保有しているという発想。・・・第二次大戦以降は植民地支配が挫折してゆき、・・・ヨーロッパの歴史、ヨーロッパの時間というもの自体が、実は人類の歴史、人類の時間のなかでの一つの歴史であり、一つの時間であったと考えざるを得ない。そこで出てくるのが構造主義の人類学であり、構造主義の言語学じゃないか。・・・≪トポス=場≫をヨーロッパの時間概念や歴史概念に従って分析するのでなく、まず空間のほうから考えていこうとする。そのとき構造主義は、十九世紀的な歴史観へのアンチとして自らを設定せざるを得なかった。・・・新しい歴史学をつくらねばならない・・・新しい歴史学とは何かという問題が出されてきたのだと思う。・・・」