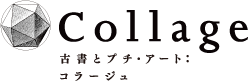「加藤:ぼくはこんどの丸山さんの解説を読んで実におもしろかった。丸山さんが≪古層≫という言葉でいっていることは、持続低音として続いているというわけでしょう。主旋律は時代によって違う。それはたいてい外からのインパクト、まあ簡単にいえば、仏教と儒教と西洋思想ですね、それとの接触から出て来る。しかし、持続低音はずっと同じ調子で続いている、という考えでしょう。・・・ぼくは非常にうまい比喩だと思う。日本文化史のすべての面について、そういえるのじゃないかと思うんです。
だから、主旋律というか、はっきり表現された意識的な世界観は外国思想とのぶつかり合いで出てくるのだが、≪古層≫としての持続低音は何か。ぼくは日本の文化史というもの、それから美術史でもある程度まで、そういう形で整理できると思うんです。ただ美術史のほうは、持続低音のほうの直接的な表現が少ないから、文学史よりはむずかしい。・・・
それから主旋律のほうでも、外国から入って来たものが日本で微妙に変る。変るのは持続低音があるからだということでしょう。だから、はっきり表現された主旋律が外国の原型とどう違うかということを分析すれば、その違いをつくり出した持続低音を推定することが出来る。こういう基本的な考え方は、日本歴史を思想的に捉えるとき、唯一の有効な捉え方ではないか、とさえ思っています。
それならば持続低音の内容はどうかということが次の問題になるわけだけれど、その前に、持続低音が本当に持続していることについて。外からのインパクトがあっても、丸山さんのいう歴史意識の≪古層≫は今日に至るまでついに消えていないといことですね?
丸山:そう思うのです。ただ、持続低音はそのままでは独立の楽想にならない。主旋律のひびきを変容させる契機として重要なんですね。≪古層≫を固有のイデオロギーとして実体化しようとした試みは、神道から日本主義まで色々あったけれども、そこには無理がある。さりとて、外来の思想の輸入の歴史というふにもわりきれない。そこが日本の思想史の難しいところで、また面白いところでもある。
加藤:・・・それから丸山さんのいわれる≪なる≫ということ、≪おのづからなる≫ということですね。そこでちょっとユダヤ教のことに触れていますね。ユダヤ教の≪つくる≫文化は、主体性の問題として、人間中心になると思うんです。押しつめていえば、歴史というものを、歴史に参加する人格の決定の積み重ねと見る。・・・絵巻ものでもそうですが、日本美術の一つの特徴は、人物中心じゃないことですね。・・・3,4年前かな、シャガールが≪旧約聖書≫の主題で連作油絵を展覧したことがあった。シャガールはユダヤ人でしょう。ユダヤ教の感覚がよく出ているなと思いましたね。たとえば≪ノアの箱舟≫。洪水になってノアだけが助かるわけでしょう。そういうのをシャガールは、人間を真中に大きく描いて、水が右側に少しあって左側に小さな舟がある。日本の画家ならば、そうは描かないでしょう。シャガールの≪旧約≫は、徹底的に人間中心主義ですね。
丸山:・・・そのシャガールの連作をぼくは見ていないけれど、日本だったらむしろ逆に、北斎が描いているような怒涛を大きく描いて、そのなかで木の葉のように翻弄される孤舟を、ダイナミックに描くでしょうね。だから、非人格的な大きな流れの≪いきほひ≫として歴史が実感されている。・・・
加藤:いまシャガールといったのは、ユダヤ教の象徴としてでね、洪水よりも大きく中央に立ちはだかるノア、天に昇る梯子よりもはるかに大きいヤコブ。いわば一人の人間が全責任において歴史を決定する。日本的な≪なる≫と対照的で、両極端だと思いますね。そういう意味では、中国は根本的に西洋に近い。『史記』の世界観、つまり一個の人間が決定するという・・・」