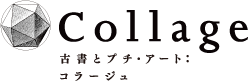フランスの代表的な哲学者三名を取り上げながら、彼らを語るとはどういうことなのか、さまざまな問いを投げかける批評。
「・・・あのフーコー、あのドゥルーズ、あのデリダとして誰もが知っている人称性の濃い三人の個人は、・・・それぞれ≪哲学者≫と呼びうる存在である。だが、それをめぐって語られる三つの挿話からなる『フーコー・ドゥルーズ・デリダ』は≪哲学書≫にふさわしい相貌などいささかもそなえていない。それは、このとりあえずの著者とみなしうる人間にいわゆる≪哲学≫的教養が欠けていたという理由もあろう。だが、それ以上に、この≪三つの物語≫が決して≪哲学≫の物語として語られていないという理由が見落とされてはなるまい。では、何の物語としてあるのか。とりあえず≪思考≫の物語として語られているというのが一つの答えであるかもしれない。また、言語という≪記号≫と≪思考≫との戯れをめぐる物語とすることも可能であろう。・・・あのフーコー、あのドゥルーズ、あのデリダは、ともにヨーロッパと呼ばれる限られた世界で≪思考≫とされ≪記号≫とされてきたものを改めて検証し、そうした歴史と現状とを鋭く批判しているとみられなくもない。・・・だが、もし事態がそう簡単に運ぶのであればすべては思想史の問題に還元され≪三つの物語≫もまた≪哲学≫の物語として語らえればそれで十分であったろう。しかし現実はそうではない事態が起こっている。また、そう読まれてならないと、この三つの挿話がいたるところでつぶやいているのだ。・・・」(「とりあえず」の序章より)