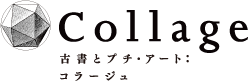「・・・“グロッタ”といっても、けっして、クルった言葉ではない。Grottaは、洞窟を意味する語で、“怪奇な”“異様な”という意味の“グロテスク”という言葉の語源になった言葉である。
ところで、事物が素直に人間の命名式にたちあい、その手のなかでおとなしくしている間は(じつは、そんな振りをしているだけなのだが)、人間は世界に安住し、ある様式、ある秩序形態の上に、すべてが和合している社会が保たれる。しかし、事物と人間の関係が険悪になり、事物がおとなしい飼猫から、一キョに獰猛な野獣に化し、いままで隠していた牙をむき出して人間にせまってくると、もうそれまでの言葉という網は、なんの役にもたたなくなる。むしろ、ひとは、命名することによって事物を懐柔しつづけてきたという幻想のはかなさに、その傲慢な野心の無意味さに、思いいたるだろう。(西欧文化を、ホンヤク語を通して輸入してきたわが国では、文化の歴史とは、このホンヤク語自体の歴史にほかならない。理性といい、意識といっても、それらの言葉は、原語のもつ長い歴史の重みを剥奪されている。そんな歴史の重みをもたぬ言葉で、いやおうなく、事物と接触しなければならないぼくらの様相は、たしかに特殊なものに違いない。)
ルネッサンス以来の傲岸な人間中心主義が、ついに事物全体の怒りを爆発させたところに、二十世紀の大変動の意味があるのだろう。人間が命名によって事物を掌中に収めていたユマニスムが崩壊し、人間が事物の一種にほかならないこと、そして、事物とは、もともと、柔かな人間の白い手に負えるものではないことを、壮絶に感じとったとき、むしろ、事物に対して人間を解体し、おしつめてゆくことが、新しい人間と事物のドラマにおいて、事物の本性にたちむかう人間の武器のひとつになる。それを手段に、人間は、事物にむかって自己を客体化してゆくのにちがいない。
“グロテスク”という言葉は、今日、そういう事物への新しいかかわり合いのきっかけになる言葉のひとつではないだろうか。・・・」