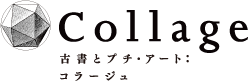「・・・それにしても、人間の愛には、このような執着もあったのか。植は、真理子に対する己れの愛情を、静かに見詰めることができそうな気がした。裏切られたからといって、何も言わずに家を捨て、やくざな生活に流されながら、過去を恨むような女々しい男に、本当の愛が燃えるはずはなかったのだ。本当の愛とは執着ではないか。植はふと伊津子のことを思った。が、今の彼は、廃人の夫から妻を奪ってしまうほどの執着を伊津子に抱いてはいない。植は、ひどい疲労を覚えた。ふと、都会の泥のような人間関係の、わずらわしさから脱したい気がした。故郷の岩手富士の秀峰が、とぼとぼ歩む彼の脳裡をよこぎった。」
「・・・この長編小説はハードボイルドの手法を使って珍しく成功している。日本の現実というより大阪の庶民の生活が、全編を強いリアリティで支えている。医学者の世界に代表される日本の上流知識人階級の歪んだ習慣と、大阪の貧民街の与太者や娼婦などに代表される日本の下層社会の歪んだ日常とが、阿倍野病院という貧民街の中にあるキリスト教慈善病院の中で烈しく、そして陰湿にぶりかりあう。阿倍野病院はこの二つの異った力の場が重なりあう、異常に歪んだ空間と言ってよい。この異常空間こそ、偏執や嫉妬に狂った人間、孤独に閉ざされた妄想、世の常識からはずれた心理、非人間的な出世欲、デカダンス、ニヒリズム、無気力、そして情欲、犯罪などが百鬼夜行する場である。・・・
読者は女というものの中に潜んでいる怪物をひとつひとつ見せられ、女の持つ不可解さを改めて認識するだろう。女にとって愛と性がいかに大きな比重を占め、それによって人生が決定されてしまうことを見るだろう。また医者の世界の封建制、非人間性を、ベンケーシー的な活躍をする植の中にも、非人間的なものが同居するこの特殊な世界を垣間見、ある深刻な感慨を受けるに違いない。
この病院に出入りする大阪の貧民街の庶民たちの風俗や習慣やあ人情が釜ヶ崎などにくわしい作者によってさすがにあざやかにとらえられていて、この小説のリアリティを支えている。彼独特のあらっぽい、けれど粘りつくような文体も、大阪の貧民街の人々を描く時はふさわしい迫力を持つ。・・・作者のさまざまな体験とその文学的可能性を集大成した、代表的作品と言ってよいであろう。・・・」(奥野健男による文庫判「あとがき」より)