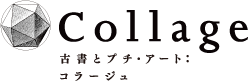ミッシェル・フーコーによる文学批評(ブランショ、バタイユ、クロソウスキー)。
「今やわれわれは、長いあいだわれわれにとって目に見えないものだった空洞を前にしている―言語の実体(エートル)がそれ自体に対して姿を現わすのは、主体の消滅のうちにおいてのみなのだ。どうやって、この異様な関係への手がかりをつかめばよいのか。たぶんそれは、西欧文化がその余白の部分において、まだおぼつかないその可能性を素描してきた、思考の一形態によってである。あらゆる主体=主権性の外に身を保って、いわば外側から諸限界を露呈させ、その終末を告げ、その拡散を煌めかせ、その克服しがたい不在のみをとっておく、そんな思考、そして同時にこの思考はあらゆる実証性の入口に位置するのだが、そのことはこの実証性の基盤ないし正当化を把握するためであるよりよりも、それが展開される空間を、それの場となる空虚を、それが成立する距たり、視線が注がれるやいなやその直接的確実性の数々が身をかわしてしまう距たりをふたたび見出すためである、―この思考は、われわれの哲学的反省の内面性、およびわれわれの知の実証性との関係からみて、一言で言えば≪外の思考≫と呼び得るであろうものを形成しているのである。」