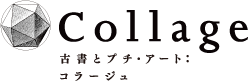同志社大学で宣教師として滞在した、オティス・ケーリによる戦争体験記。
「・・・私はこのごろ、デモクラシーという言葉を出来るだけ使わないようにしている。というのは、連中と話していると“それは何デモクラシーのことですか”などと、よくいわれる。また、ある男は“デモクラシーという言葉を使うと、アメリカにおべっかを使っているみたいでいやだ”という。
そういう厄介な言葉は使わない方がいいと思っている。それに、この言葉は、戦後の日本で、心ない人たちに、すっかり汚されてしまった。“デモクラシーのために・・・”“民主日本のために・・・”と、戦時中の“大東亜共栄圏のために・・・”と同じように、枕言葉のようにされてしまった。どこの会議でも、どこの催でも、一応、そういうあいさつをしないと、かっこうがつかないといった傾向だ。
どういう言葉で、これにおきかえるか。私は“人間主義”ということにしたい。あらゆる既成概念をとり払って、人間と人間が裸でふれ合い、ぶつかり合うことだ。
こんど私は、二年と七ヶ月敗戦の日本にいたわけだが、一部のアメリカ人が
謳歌するように、日本の民主化は達成されたなどとは、どうしても思えない。ロクに戦争の反省もしないうちに、もうこのくらいで勘弁しろよといった顔付きで、“デモクラシー”のスカーフで頬被りしてしまった。敗戦を終戦といい、占領を進駐といいくるめた“ミゾリー”直後の日本を、私は歯ぎしりして眺めた。そして一昨々年の秋、女房ともども腕まくりで日本へ来た。私が進駐当時会った文化人たちは、これはと思った人々まで、そのころの情熱を打算におきかえ、流れの上へ自分をのっけてゆくことに窮々としている。医学の研究も棒に振ったが家庭生活というものもないじゃないかと、女房にこぼされるほど、この二年余り駆けずり回った。徒らに忙しかったと、憮然と振り返るだけで、快く胸に下りてくるものがない。
いずれまた日本に来ることになるだろう。それは私の宿命だ。この次には、どんな心境で、どんな肩書きで来るかまだ分からない。そのとき、日本がどうなっているかも予測は出来ない。アメリカとソ連という二つの世界に、びっしりと挟まれ、二つの勢力が、狭い圏内で、音もなくひしめいている。その間隙を縫って、消滅したはずのミリタリズムらしきものが、チラチラと覗く。
経済的な建て直りろくに出来ないうちに、日本は先鋭化した国際政治の中へ引き込まれて行くようだ。何か私には及びもつかないとこへ走ってゆくような不安を覚えながら旅の支度をしている。」(日本の若い者おわり)