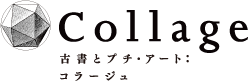「僕が向うにいた時に、放送局が持っている交響楽団の定期公演で、マーラーの『大地の歌』を聴いたことがある。・・・僕は大して期待をもって行ったわけじゃない。・・・しかし曲が始まると、第一楽章の最初のモチーフが既に告別への予感を奏でていた。それが奇妙に僕の心に突きささった。これは西欧の人間の単なるエクゾチックな共感といったものじゃなかった。ヘッセの『シッダルータ』なんかとも共通するもので、作者自身が彼の東洋を内部に持っていることを証明するものだ。第一楽章は『大地の悲哀を歌う酒の歌』だ。大地と普通は訳すけれど、あれはつまり現世ということだ。現世に於て、酒に酔い一時の夢を貪り、生きることをエンジョイしても、告別への予感はいつでも低音で響いている。第四楽章や第五楽章は比較的明るくて、現世の愉しさを歌っているが、たちまちあの長い第六楽章の『告別』が、ピアニッシモの弦の上にオーボエで主題をひびかせるのだ。僕がその時感動したのは、ヨーロッパの本場での演奏が素敵だとか、僕が日本へ帰る日が近づいたとかいうことじゃなく、つまり人生の本質というものが、アルトの独唱に乗って、僕自身の魂の旋律となって心の中でひびきはじめたからだろうな。『私は故郷を求めてさ迷う。』たしかにそうだ。ただ僕たちはこの世に於て、何処にその故郷があるのか知らないんだよ。」
「・・・『風土』あるいは『塔』いらい、長編小説、短編小説を問わず、福永氏の小説が死の観念、死の意識を中枢として書かれているのは、いまさら思い出すまでもないことである。どの作中人物も例外なしに死の影のなかにふかぶかと沈み、死に固く縛られながら日常の時間の流れを生き、彼らにとって、死は生の本質的な部分をなしている。いいかえれば、福永氏の小説は、存在の隅々まで死の観念に呪縛され、死の意識に支配されつくしている人間の内面を造型する小説なのである。
しかし光があってはじめて影が落ち、光の明度がませばますほど影も濃くなるのと同じように、ひとりの人間のなかで、死の意識の量が大きくなればなるほど、それと正比例するようなかたちで、生の意識もするどく研ぎ澄まされるものであるにちかいない。つまり、死を考えるのは生を考えることでもあり、ふだん日常の生活の流れにまぎれて意識の閾の下に覆いかくされている死が、なにかのきっかけで意識の表面に露頭するその瞬間から、・・・人間は、・・・生の本質とはなにかと問いかけずにはいられなくなる。・・・」(菅野照正『告別』1973年講談社文庫版掲載解説より)