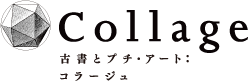「“目の下に新しいものなし”とは、遠い昔から伝えられて来た人類の智慧である。すべてを歴史の流れの中において見る時、どんなに突飛と思われる事象も、綿密にはりめぐらされた運命の網目の中に捉えられ、“歴史的必然”の中に解消させられてしまう。芸術作品といえども、無論例外ではない。どのように独創的作品でも、どんなに“異端”の芸術家でも、必ずそのよって来るべき過去を持っており、与えられた条件の中でのみそうあり得たような歴史的側面を持っている。・・・しかしながら他方、別の見地に立って見れば、独創性こそは、どのようなかたちをとってあらわれるにもせよ、それなくしては芸術作品の存立そのものの根拠が失われるような何ものかであると言うことができる。われわれが、何にせよ、ある作品を芸術と認めることができるのは、そこに他の何ものにもかえがたい“あるもの”、与えられたどのような条件にも還元し得ぬ特質を感得すればこそにほかなるまい。そしてそれこそが、“独創性”と呼ばれるものでなくて何であろうか。・・・もしこのような二律背反が解決され得ないものであるとすれば、人は芸術作品を前にして、“独創性”か、“歴史性”か、そのいずれかに賭けねばなるまい。事実、十九世紀後半の西欧の芸術理論は、芸術作品における“歴史性”の優位を主張するものと、“独創性”への信頼を出発点とするものは、はっきりとふたつの立場を示していた。・・・歴史的条件と個人の独創性とのこのような複雑なからみ合いの様相を、ピカソほどまざまざとその作品の中で見せてくれる芸術家は、他に例が少ないと言ってよいであろう。奔放自在なその創造力、溢れるように豊かなその独創性を否定するものはまずあるまい。それでいてまた、ピカソほど密接に歴史と結びついている芸術家も珍しいのである。・・・」