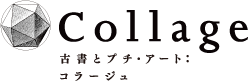「・・・近代資本主義の精神の、いやそれのみでなく、近代文化の本質的構成要素の一つというべき、天職理念を土台とした合理的生活態度は―この論稿はこのことを証明しようとしてきたのだが―キリスト教的禁欲の精神から生まれたのだった。読者はここでいま一度、この論稿の冒頭で引用したフランクリンの小論を読みかえして、その個所でわれわれが≪資本主義の精神≫とよんだあの心情の本質的要素が、さきにピュウリタンの〔天職意識に由来する〕職業的禁欲の内容として析出したものと同じであって、ただフランクリンのばあいには、宗教的基礎づけがすでに生命を失って欠落しているにすぎない、ということを見とどけていただきたい。―近代の職業労働が禁欲的性格を帯びているという考えは、決して新しいものではない。専門の仕事への専念と、それに伴うファウスト的な人間の全面性からの断念は今日ではどうしても切り離しえないものとなっている。・・・ピューリタンは天職人たらんと欲した―われわれは天職人たらざるをえない。というのは、禁欲は修道士の小部屋から職業生活のただ中に移されて、世俗内的道徳を支配しはじめるとともに、こんどは、非有機的・機械的生産の技術的・経済的条件に結びつけられた近代的経秩序の、あの強大な秩序界を作り上げるのに力を貸すことになったからだ。そして、この秩序界は現在、圧倒的な力をもって、その機構の中に入りこんでくる一切の諸個人―直接経済的営利にたずさわる人々だけではなく―の生活のスタイルを決定しているし、おそらく将来も、化石化した燃料の最後の一片が燃えつきるまで決定しつづけるだろう。バックスターの見解によると、外物についての配慮は、ただ≪いつでも脱ぐことのできる薄い外衣≫のように聖徒の肩にかけられていなければならなかった。それなのに、運命は不幸にもこの外衣を鋼鉄のように堅い檻としてしまった。禁欲が世俗を改造し、世俗の内部で成果をあげようと試みているうちに、世俗の外物はかつて歴史にその比を見ないほど強力になって、ついには逃れえない力を人間の上に振るうようになってしまったのだ。今日では、禁欲の精神は―最終的にか否か、誰が知ろう―この鉄の檻から抜け出してしまった。ともかく勝利をとげた資本主義は、機械の基礎の上に立って以来、この支柱をもう必要としない。禁欲をはからずも後継した啓蒙主義の薔薇色の雰囲気でさえ、今日ではまったく失せ果てたらしく、≪天職義務≫の思想はかつての宗教的信仰の亡霊として、われわれの生活の中を徘徊している。・・・
将来この鉄の檻も中に住むものは誰なのか、そして、この巨大な発展が終わるとき、まったく新しい預言者たちが現れるのか、あるいはかつての思想や理想の力強い復活が起こるのか、それとも―そのどちらでもなく―一種の異常な尊大さで粉飾された機械的化石と化することになるのか、まだ誰にも分からない。それはそれとして、こうした文化発展の最後に現われる≪末人たち≫(letzte Menschen)にとっては、次の言葉が真理となるのではないだろうか。≪精神のない専門人、心情のない享楽人。この無(ニヒツ)のものは、人間性のかつて達したことのない段階にまですでに登りつめた、と自惚れるだろう≫と。」
【関連書】
マリアンネ・ウエーバー『マックス・ウエーバー Ⅰ、Ⅱ』(1963、みすず書房、初、カバー(少痛み)、帯(少焼け)、四六版、272P[Ⅰ]、270P[Ⅱ]、大久保和郎訳)
2,000円
妻によるウエーバーの評伝。
「これは、一つの時代がその終焉に当たってもう一度自分の価値を総括してみようとするとき
いつもあらわれて来る人間だった。
そのような時、一人の人間があって、時代のすべての重荷を取り上げ、
自分の胸の奥底へ投げ込むのだ。
彼に先立つ人々は人の世の悲喜と甘苦しか知らなかったのに、
彼はひたすら人生の重み厚みを感じ、
すべてを一つの≪物≫として自分が抱き止めるのを感じる―
ひとり神のみが彼の意志を高く超えている。
さればこそ彼は、この超絶を憎む雄々しい心をもって
神を愛するのだ。 R・M・リルケ」
「・・・二十世紀初頭のヨーロッパの精神会において、マックス・ウエーバーの姿が巍峨たる一つの巨峰をなす。あたかも≪古き神が死に、新しき神のいまだ生れざる」この時期に、彼は一方で十九世紀の知的遺産を批判的に継承し、他方では二十世紀の渾沌として現状をまともに凝視しながら(だからこそ彼の射程は二十世紀後半に入ったわれわれの時代にまで達しているのであるが)、その時代の悲劇性をみずからの肩に担って生きた。しかも、その彼自身の肉体のうちにも非劇的なものはひそんでいたのである。彼はその両方の非劇性にまことに強靭な倫理観をもって堪えた。この生涯を描くマリアンネ婦人の筆にはパテーティッシュな情熱が感じられる。まさにそれは、愛情と敬意に満ちた≪Ecce Home≫の叫びであり、この浩瀚な、決して読みやすいものではない伝記を感動的な人間記録としているのである。・・・」訳者 あとがきより