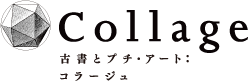西欧と日本という東西二つの異質文化がぶつかり合う接点としての科学の移入の歴史を論じた書。
「日本が、科学を技術と考え、自然をコントロール手段とみなし、日本人自身の奥底にある独特の自然との付き合い方には手をつけずに、問題解決、目的達成の道具、器械として西欧科学を処理できる時代は、ようやく終わりつつある。科学・技術は、現在では、われわれ一人一人を、いやおうなく縛る思考上の枠組みとして、自然に対する西欧的な≪なぜ≫の追及方法を強制しているばかりではない。それに付随してもたらされた社会機構が、科学・技術を自らの都合の良いように利用する、という現象、つまり科学する主体の側が、造り上げた社会機構の束縛から自由になりえない、という体制的な欠陥が、現在の日本にも、太平洋戦争当時と同じように、より深刻な形で起こりつつあると、と言えないこともなかろう。したがって、どういう社会機構、社会体制が科学・技術を最も全人類の幸福のために役立たせうるか、ということも、一つの大きな問題として見のがすわけにはいかない。
科学・技術はそれだけで独立している客観的で唯一至上の体系ではけっしてない。それと結びつく社会機構や基本文化、そしてその奥に存在するわれわれ人間を除いて科学・技術を語ることは無意味である。日本の科学・技術を論じるに当たって、日本の社会構造、日本の思想構造、日本人としての意識などとの結びつきを、世界のなかで考えることこそ、最も重要ではあるまいか。」