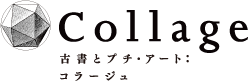遠藤文学の初期世界にみられる西欧と日本との間の人種差別に起因するテーマを扱った長編小説。
「”・・・憐憫はたくさんです。そっとしといて下さい。ぼくらを探さないで下さい。
ムッシュウ・イアラ、君のノートの中にもそんな言葉がたくさん書いてありましたね。無記名の人間になりたい。カメラの位置をどこにも固定したくないですか。・・・なるほど、あれは黄色人でも白人でもない一人の人間になりたい君の気持ちでしょうね。笑いながらクロスヴスキーはその顔を近づけてきた。”
『青い小さな葡萄』はキリスト教の真実を真向うから問いつめようとした作品なのかもしれない。そもそも≪青い小さな葡萄≫とは何だろうか。不毛の地に稔るヴァルツの葡萄。スザンヌ・パストルがナチ兵・ハンツに与えた葡萄。作者はその葡萄になにを託そうとしたのだろうか。人間の善意、人種、国境をこえたヒューマニズム、≪青い小さな葡萄≫はたしかにそのようなキリスト教精神を象徴しているだろう。元ナチ兵・ハンツがスザンヌ・パストルを探し求めてフランスにやってきたのも、スザンヌに会い、自分を助けてくれた善意にあらためて礼をいうためだった。また、井原がハンツの語る美談を疑いながらも、ハンツと一緒にスザンヌの消息を探し歩くのも、不信の時代(戦争時代)に実った善意と信頼の葡萄の在りかをみずからの眼でたしかめようとしたからなのだ。そういう善意が信じられるのは人種、国境が違っても、そこに共通の信仰や共通の理想があるからなのだろうか。それとも、たとえあたりに憎悪と不信がたれこめていても、個人のなかになおかつキリスト教の精神が健全に生きているからなのだろうか。キリスト教はどこまでも信頼しうるか、キリスト教国民は非キリスト教国民とくらべてはたしてどこまで優っているか、『青い小さな葡萄』が問うのは、いわばこのようなキリスト教の真実なのである。」
(武田友寿による解説より)