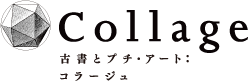世界と人間存在をめぐる思索と表象としての二項対立的思考は、古今東西を問わず、一つの認識論的枠組み(パラダイム)を今なお提供しています。生と死(エロティシズム)、東と西(オリエンタリズム)、南と北(格差問題)、男と女(ジェンダー)、光と影、善と悪、文化と自然、など、異なる諸力や価値体系が衝突し、争いの火種を播く対立となることもあれば、異質なるもののケミストリー(化学反応)や融合がポジティブな変化や発展につながることもあります。東西の識者によるパサージュとアーティステックな表象を通じ、こうした二元論に起因する諸問題やその根源にあるものについて再考する機会の創出を試みます。
「死とエロス」は人間存在を考える上で重要なテーマです。今回のプチ・ギャラリーでは、フランスの思想家ジョルジュ・バタイユによる『エロティシズム』および言語哲学者丸山圭三郎による『ホモ・モルタリス:生命と過剰』からのパサージュとともに本テーマとも関連する、美術家の作品を紹介します。
「エロティシズムとは、死におけるまで生を称えることだと言える。・・・生殖のための性活動は有性動物と人間に共通の事柄なのだが、しかし見たところ人間だけが性活動をエロティックな活動にしたのである。エロティシズムと単純な性活動を分かつ点は、エロティシズムが、生殖、および子孫への配慮のなかに見られる自然の目的[種の保存・繁栄]とは無関係の心理的な探究であるというところなのだ。・・・これから私は、不連続な私たちにとって、死が存在の連続性という意味をもつことを明示しようと思う。たしかに生殖は存在の不連続性につながっている。だが他方で生殖は存在の連続性を惹き起こしもするのである。つまり生殖は密接に死と結びついているのである。私は、まさに死と存在の生殖について語ることによって、死と存在の連続性が一致していることを明示してみたいと思っている。というのも、死も存在の連続性も、ともに魅惑するものだからだ。そしてこの双方の魅惑こそがエロティシズムを支配しているのである。」
(ジョルジュ・バタイユ『エロティシズム』2004、筑摩書房、酒井健訳)
「後期フロイトが、それまで生物の二大本能とみなしていた、①個体維持のための食欲の源である〈自己保存欲動〉と、②種保存のための性欲の源である≪性欲動≫の対立、≪飢餓と性愛≫とも言うべき対立を解消し、両者ともエロスという≪生の欲動≫に包摂し直したことはよく知られていよう(『快楽原則の彼岸』、1920年)。そして二元論好きのフロイトが、≪生の欲動≫に対立する新たな項として≪死の欲動≫を立てたことも有名である。・・・しかしエロスとタナトスを対立させることは出来ないだろう。いずれも同じ生の円環運動上の一通過点であり、ヴェクトルの違いがあるだけなのだ。私の≪死のコスモソフィー≫は同時に≪生のコスモソフィー≫である。狭義の生(=食と性)も死も、ともに大きな生に包摂されて、その対立項はない。円環上の一点一点が、死を孕んだ生であり生を孕んだ死であると言ってもよい。一方のヴェクトルはカオスの不連続化・拘束に向かい、他方のヴァクトルは連続への回帰・解放に向かう。そして生の快楽、すなわちエロティシズムは、昇華と排除によって生ずる。・・・」
(丸山圭三郎『ホモ・モルタリス:生命と過剰』1992, 河出書房新社)