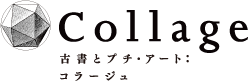日本人論の古典の一冊。 「≪われわれ日本人≫に表されている日本人の集合的アイデンティティーが、西洋人のそれと違って個人的レベルのものではなく、超個人的な血縁的、それも血縁史なアイデンティティーであるということ、これが本書において最初に押さえておきたい一つの眼目である。この血縁史的アイデンティティーは、実に多くの「日本固有」の現象を説明する鍵になる。例えば中根千枝氏のいわゆる≪タテ社会≫をとってみても、これはいわば、この血縁史的アイデンティティーが、現在の時点に投影されたものにほかならないし、土居健郎氏のいう≪甘え≫にしても、このアイデンティティーが現実の対人関係の場面に投影 »続きを読む
人文科学
1974、弘文堂、初、函(数か所に染み)、四六版、238P
『ローカル・ノレッジ:解釈人類学論集』
1991、岩波書店、初、カバー、帯、B6版、424P
2,500円
「とどのつまるところ、またそもそもの初めから、文化の解釈学的研究とは、人間が生を営むという行為において生を構築する際の多様性と調和しようとする試みである。・・・他の人々がわれわれを見るようにわれわれ自身を見ることは、目を開かせるものとなろう。他の人々にもわれわれ自身と共有するところがあるとして見ることは、最低限の心得である。しかし、われわれ自身を他の人々のさなかに見る、すなわちわれわれ自身を、人間の生がある地でとったかたちの固有(ローカル)の実例として、諸事情の中の一事例、諸世界の中の一世界として見るというはるかに大きな困難を達成して初めて、それなくしては客観性は自己賛美と »続きを読む
『現代哲学』
1969、日本放送出版協会、初、カバー(少汚れ)、B6版、帯、204P
1,000円
フッサール、メルロ=ポンティ、サルトル、レヴィ=ストロースなどの論理を辿り、現代哲学の中心的課題を明白にする。 「・・・ヘーゲルにせよ、マルクスにせよ、それぞれの流儀で当代の政治や科学や芸術などとの対話を試み、そのなかから自己の哲学を作り上げてきているわけである。メルロ=ポンティ自身もあるところで、哲学というのは≪どこにもありどこにもない≫(partout et nulle part)ものだ言っているが、たしかに哲学というものは知のどの領域にでもあるが、といって哲学に固有の領域などというものはどこにもないもののようである。むしろこういうふうに、当代の政治や科学や文化の諸領域 »続きを読む
『背徳のメス』
1960年、中央公論社、初、函(少痛み)、直木賞、四六版、P241
00円 (在庫なし)
「・・・それにしても、人間の愛には、このような執着もあったのか。植は、真理子に対する己れの愛情を、静かに見詰めることができそうな気がした。裏切られたからといって、何も言わずに家を捨て、やくざな生活に流されながら、過去を恨むような女々しい男に、本当の愛が燃えるはずはなかったのだ。本当の愛とは執着ではないか。植はふと伊津子のことを思った。が、今の彼は、廃人の夫から妻を奪ってしまうほどの執着を伊津子に抱いてはいない。植は、ひどい疲労を覚えた。ふと、都会の泥のような人間関係の、わずらわしさから脱したい気がした。故郷の岩手富士の秀峰が、とぼとぼ歩む彼の脳裡をよこぎった。」 「・・・こ »続きを読む
『日本の若い者』
1950、日比谷出版社、カバー(背焼け)、本体全体に経年焼け、装丁:向井潤吉、
巻頭の著者近影写真、306P
00円 (在庫なし)
同志社大学で宣教師として滞在した、オティス・ケーリによる戦争体験記。 「・・・私はこのごろ、デモクラシーという言葉を出来るだけ使わないようにしている。というのは、連中と話していると“それは何デモクラシーのことですか”などと、よくいわれる。また、ある男は“デモクラシーという言葉を使うと、アメリカにおべっかを使っているみたいでいやだ”という。 そういう厄介な言葉は使わない方がいいと思っている。それに、この言葉は、戦後の日本で、心ない人たちに、すっかり汚されてしまった。“デモクラシーのために・・・”“民主日本のために・・・”と、戦時中の“大東亜共栄圏のために・・・”と同じように、 »続きを読む