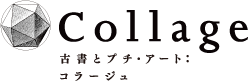ミッシェル・フーコーによる文学批評(ブランショ、バタイユ、クロソウスキー)。 「今やわれわれは、長いあいだわれわれにとって目に見えないものだった空洞を前にしている―言語の実体(エートル)がそれ自体に対して姿を現わすのは、主体の消滅のうちにおいてのみなのだ。どうやって、この異様な関係への手がかりをつかめばよいのか。たぶんそれは、西欧文化がその余白の部分において、まだおぼつかないその可能性を素描してきた、思考の一形態によってである。あらゆる主体=主権性の外に身を保って、いわば外側から諸限界を露呈させ、その終末を告げ、その拡散を煌めかせ、その克服しがたい不在のみをとっておく、そん »続きを読む
古書&アート作品
1978、朝日出版社、初、カバー、帯(少背焼け)、新書版、140P、豊崎光一訳
『臨床医学の誕生』
1969、みすず書房、初、カバー、菊判、316P、神谷美恵子訳
2,500円
「臨床医学的経験とは、西洋の歴史の上で、具体的な個体が、初めて合理的な言語にむかって開かれたことを意味するのであって、人間対自己、及びことば対もの、という関係における重要な事件である。・・・ここで企てられた研究は、したがって、指示を与える意図はまったくなく、現代の医学的経験を可能ならしめた諸条件をはっきりさせ、批判的であろうとする意図的な計画を意味する。・・・他の場合と同様に、ここでも問題は、一つの構造論的研究なのである。この種の研究は、歴史的なものの厚みの中で、歴史自体の諸条件を解読しようと試みるものである。人間の思考のなかで重要なのは、彼らが考えたことよりも、むしろ彼ら »続きを読む
『我と汝・対話』
1978、みすず書房、初、カバー、三方経年少焼け
1,500円
「世界は人間にとっては、人間の二重の態度に応じて二重である。人間の態度は、人間が語り得る根元語が二つであることに応じて二重である。この根元語とは、単一語ではなく対偶語である。根元語のうちのひとつは対偶語・我―汝である。もうひとつの根元語は対偶語・我―それであり、この場合には、それを彼あるいは彼女のいずれかで置きかえても、その意味するところには変りがない。このように根元語が二つあるからには、人間の我もまた二重である。なぜなら、根元語・我―汝における我は、根元語・我―それにおける我とは異なっているからである。」
『告別』
1962年、講談社、初、カバー、帯(背少焼け)、四六版
00円 (在庫なし)
「僕が向うにいた時に、放送局が持っている交響楽団の定期公演で、マーラーの『大地の歌』を聴いたことがある。・・・僕は大して期待をもって行ったわけじゃない。・・・しかし曲が始まると、第一楽章の最初のモチーフが既に告別への予感を奏でていた。それが奇妙に僕の心に突きささった。これは西欧の人間の単なるエクゾチックな共感といったものじゃなかった。ヘッセの『シッダルータ』なんかとも共通するもので、作者自身が彼の東洋を内部に持っていることを証明するものだ。第一楽章は『大地の悲哀を歌う酒の歌』だ。大地と普通は訳すけれど、あれはつまり現世ということだ。現世に於て、酒に酔い一時の夢を貪り、生きる »続きを読む
『ふさがれた道:失意の時代のフランス社会思想 1930-1960』
1979年、みすず書房、カバー、天と地に少経年やけ、菊判、203P
1,000円
「・・・≪ふさがれた道≫というモチーフ、行き止りの小路と閉された見通し、よろめきと手詰り、ますます絶望的となる脱出口の模索というモチーフは、第一次世界大戦の勃発に続く半世紀近くを通じて、あらゆるタイプ、あらゆる知的関心のフランス人の思考に滲みわたっているのである。それは、あたかもアラン=フルニエが、幸いかれより恵まれてあの恐るべき一九一四年という年を生きのびた同時代人たちに終生つきまとった想念、漠然たる恐れのまつわりついた、出口の定かでない暗いトンネルのような世界という感じを、大戦の1年も前に予言していたかのごとくであった。 ・・・一九三〇年から一九六〇年代初めにいたる時代 »続きを読む